ニートになった人の事情は千差万別です。
本気で就職活動をしようとするタイミングは 、個々の状況や課題が解決しないことにはなかなか前に進めないというのが現実です。
そして多くの人に共通していることは、長引くニート生活でブランクがある分、漠然とした不安や悩みを抱えているというところです。
就職を希望する気持ちはあっても、具体的にどう行動すればよいか分からないという人が多いのではないでしょうか。
手当たり次第に就職活動を行うよりも、効率的で充実した就職活動できる方法がないか考えてみたいと思います。
フリーターとニートとの違いについて
「フリーター」と「ニート」という言葉は、多くの人がきっと今までに一度は耳にしたことがあると思います。
どちらも日本で広まったのはわりと最近のことですが、二つの違いがよくわからないという人も多いと思います。
厚生労働省によると、それぞれ以下のように定義されています。
フリーターの定義は、15~34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、以下の者の合計。
- 雇用のうち「パート・アルバイト」の者
- 完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
- 非労働力人口で、家事も通学もしていない「その他」の者のうち、就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
ニートの定義は、15~34歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない方
「フリーター」は、元々は「フリーアルバイター」という言葉から始まりました。
1985年に東京のシンガーソングライターによる「フリーアルバイター」という造語を、翌年に朝日新聞が紹介したことをきっかけに全国に流行しました。
1987年にリクルート社の社員が「フリーアルバイター」を「フリーター」と略して紹介したことをきっかけに、この名前が定着しました。
一方、「ニート」の由来は「Not in Education, Employment or Training」の頭文字をとって略した言葉で1999年、イギリスの内閣府による調査報告書で初めて用いられた言葉です。
ニート人口は2002年のピーク時からほぼ横ばいに推移している
内閣府が発表した平成30年版「子供・若者白書(全体版)」によると、2017年の若年無業者いわゆるニートと呼ばれる15~39歳の若年無業者は、71万人であり、15~39歳人口に占める割合は2.1%と発表されています。
|
年齢 |
無業者数 |
|---|---|
|
15~19歳 |
7万人 |
|
20~24歳 |
14万人 |
|
25~29歳 |
15万人 |
|
30~34歳 |
17万人 |
|
35~39歳 |
18万人 |
就業希望のニートが求職活動をしない理由
職に就きたい思いはあるにも関わらず、ニートの場合、求職活動をしない理由については、以下のような理由が多くみられます。
- 病気・けがのため
- 学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている
- 探したが見つからない
- 知識・能力に自信がない
- 希望する仕事がありそうにない
「若者白書」の内容から分かることは、病気やケガによって求職活動ができない状況はやむを得ないとして、回復すれば社会復帰できる可能性は高いでしょう。
また、進学や資格取得のための勉強をしている人は、将来のキャリアや目標のための時間であり、世間がいうニートとは意味合いが違います。
しかし、求職活動をしない理由に「探したけれども見つからなかった」、「知識・能力に自信がない」という理由をあげる人もいます。
長引くニート生活の中で、社会から疎外された不安感や焦りから、引きこもりがちな生活環境が与える影響があるのかもしれません。
社会の壁にぶつかり、ニートになってしまった若者も多くいます。

ニートが有効活用できる就労支援について
ニート脱出を目指して、就職活動を成功させるためには、ポイントを押さえた進め方や下準備が必要です。
この就職活動の対策こそが、結果の明暗を分けるとても重要なプロセスになります。
しかし、ブランクがある上に学校単位で動いているわけではないニートにとって、仕事探しから書類の準備、面接対策などにすべて一人で取り組まなければならないのは、かなり大変なことです。
ブランク期間を抱えるニートにとっての不安点は、自己PRできる程の知識やスキルを持たないというケースが多いことです。
不安や焦りを抱えながら一人で就職活動を行うことは、精神的にも容易なことではありません。
この問題を解決するために行政と民間団体のネットワークによるさまざまな就職支援制度やサービスが実施されています。
1.ハローワークの求職支援
就職の窓口といえばハローワークが有名です。
職業相談、求人紹介のほかに、職業訓練や就職セミナー、講習会など、就職に関するサービスが充実しています。
求職者支援制度とは、失業手当を受けられない人が早期に就職できるよう、国が支援する制度です。
通常のハローワークの求人紹介に加え、スキルアップのための職業訓練と職業訓練受講給付金(月10万円+交通費)が受けられます。
スキルアップを目指している人は活用してみるとよいでしょう。
若年層、中高年、フリーター、引きこもりやニートなど、対象別の細やかな正社員就職のための支援制度を設けています。
ハローワークに求職者登録することで職業相談と求人の応募が可能になります。
2.厚生労働省「地域若者サポートステーション(通称サポステ)」制度
サポステは働くことに不安や悩みを抱える15~39歳までの若者を対象にキャリア・コンサルタントなどによる個別的な相談、支援計画の作成、ニートが抱えるコミュニケーション障害などを回避するための教育訓練などによるサポート、協力企業への職場体験などのさまざまな就労支援があります。
具体的な内容としては、就職コンサルタントによるカウンセリングや職場体験などの就職支援プログラム、各種セミナー、他の支援機関への誘導などがあります。
利用しやすいよう全ての都道府県に必ず設置しています(全国173箇所)。
3.地方自治体やNPO団体などによる就職支援サービス
全国にある就職を目指す若者の職業的自立を支援する団体に相談するという手段もあります。
これらの支援機関は、地方自治体やNPO法人が母体となっていることが多く、就職支援だけでなく、引きこもりや人間関係に関する不安など、ニート特有の悩み相談に乗ってくれるところも多いようです。
その中でも中心的存在として挙げられるのが、認定NPO法人育て上げネットです。
このNPO法人では「ジョブトレ」という若者に提供する就労基礎訓練プログラムを通じ、若者の働く不安を働き続ける自信に変わるというコンセプトの下、就労のために必要な支援から就職後の支援に至るまで手厚くサポートを行っています。
スタッフが相談に乗りながらサポートし、他の支援機関や団体、行政、企業との連携も含めた「包括的な支援」を実現しています
4.パーソナル・サポートセンター
分野を超えてさまざまな団体が連携し、パーソナルサポートの実施や制度化、パーソナルサポーターの育成を行い、支援を必要としている人を様々な社会福祉制度やサービス、介護事業所や福祉施設などにつなげ、その方が地域で安心して暮らすことができるようにサポートします。
家を失った人や障がいのある人、DV(ドメスティックヴァイオレンス)被害者、一人親世帯、ニート、引きこもり、就労困難者などが安定した生活を送るための総合的なサポートを実施します。
5.ジョブカフェ
ジョブカフェは通称で、正式名称は「若年者のためのワンストップサービスセンター」です。
若者が自分に合った仕事を見つけるためのいろいろなサービスを1か所で、もちろんすべて無料で受けられる場所です。
46の都道府県が設置する支援施設で、ハローワークを併設しているジョブカフェもあります。
若者能力向上、就職支援を目的に、職場体験や就職関連のサービスを受けることができます。
ジョブカフェの多くは県庁所在地にありますが、地域によってはサテライトという出張所を作ってサービスを行っているところもあります。
ジョブカフェでは、各地域の特色を活かして就職セミナーや職場体験、カウンセリングや職業相談、職業紹介などさまざまなサービスを行っています。
また、保護者向けのセミナーも実施しています。
6.就職支援サイト・人材紹介サービス
いきなり外に出て窓口に相談に行ったり職業訓練を受けたりするのは敷居が高すぎると感じている人には、インターネットの就職支援サービスや人材紹介サービス、サポートネットなどを利用するのがオススメです。
まずは、登録するだけでも、気分的に一歩前進したように感じられます。
ネットで気軽に相談できるのがメリットですが、いざとなった時は、プロの就職コンサルタントが、求人の紹介から面接対策まで、こまやかにサポートしてくれる心強いサービスです。
マイナビAGENT(マイナビエージェント)
人気企業の多くが新卒採用に「マイナビ」を利用することから、企業間のつながりが多く、幅広い求人が見られます。
20代〜30代の転職サポートに強く、関東・関西の求人が特に多いのが特徴です。
第二新卒の20代から30代前半までの若い人で、関東・関西で転職を考えている人におすすめの転職エージェントです。
マイナビエージェントの求人情報は、約80%が非公開となっています。
さらに、マイナビエージェントにしか求人を掲載していない独占求人もあります。
他では知りえない求人情報が手に入るのもマイナビエージェントの強みです。
会社側も20代の人材を募集しているところが多く、ベンチャー企業など、会社自体が若いところが多いのも特徴です。
成長意欲が高い、会社とともに成長したいと思っている方にはピッタリです。
どのように進めればいいのか分からない方でも大丈夫、まずは無料相談の申し込みからはじめましょう。
無料相談 ☞ マイナビエージェント ![]()
この他にも特色のある転職サイトがあります。
興味のある方はこちらをご覧ください。





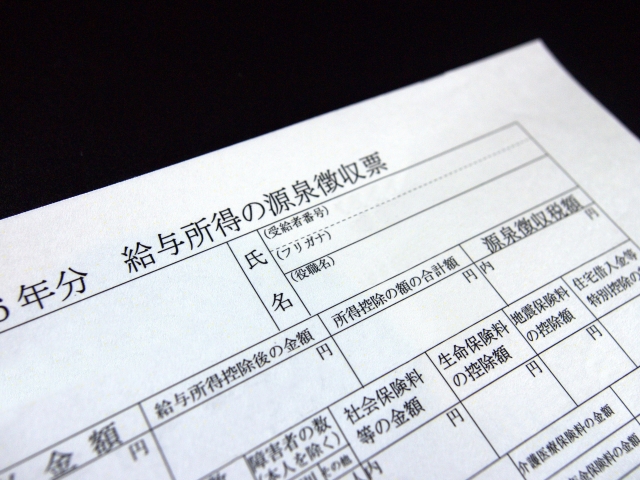
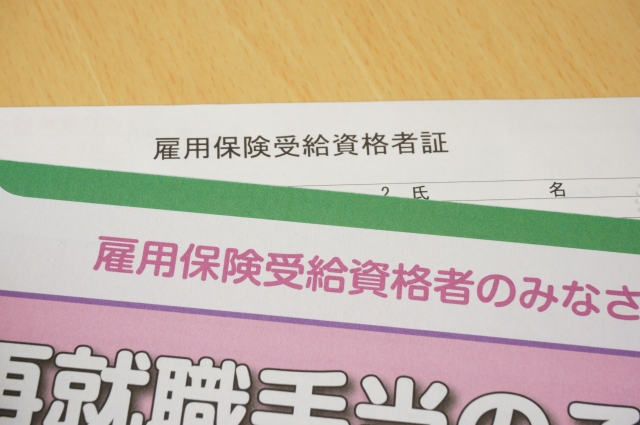
コメント