それぞれの会社にある福利厚生の一つである、家族手当、扶養手当、配偶者手当は会社ごとに支給額が異なります。
法律上義務付けられているものではなく、金額以外にも呼び方や支給条件といったものも会社によって様々です。
会社選びに関して、福利厚生も就活で非常に迷う部分になります。
膨大な数の会社があるので、そう思うのも当然です。
つい給料の高さに目がいきがちですが、福利厚生が充実しているという面もチェックしておくと、いざという時に助かる点が多いものです。
家族手当、扶養手当、配偶者手当とは?
1.家族手当とは
家族手当とは、配偶者や子供がいる社員に対して、手当という形で支給される福利厚生の一つです。
扶養している家族が多い人といない人では当然、生活にかかるお金は異なります。
そこで、家族がいる社員の金銭的な負担をできるだけ軽減する安心して働くことができるようにと取り入れられています。
家族手当は、扶養配偶者の人数によって決定されます。
扶養の基準は、税法上の扶養配偶者(年収103万円以下)としている会社が多いようです。
(1)家族手当はどのくらいの金額か
家族手当は法律上義務付けられているものではなく、支給するかどうかはその会社によって決まります。
したがって、相場という表現は適切ではありませんが、配偶者への家族手当としては1万円前後、子ども1人あたりでは3,000円から4,000円程度支給している会社が多いようです。
(2)共働き家族は要注意
家族手当の支給は会社によりますので、家族手当をどのような場合に支給したり、支給しなかったりするかも会社側の就業規則等で異なります。
共働きの場合には、会社によっては配偶者分の家族手当を支給しない場合もありますので、家族手当の支給要件は就業規則等で確認することが大切になります。
(3)家族が出来たら申告を忘れずに
家族手当は家族が出来たら自動的に支給されることはなく、通常、会社側に申告する必要があります。
したがって、家族ができたら会社側へ申告することを忘れないようにしましょう。
2.扶養手当とは
扶養手当は、基本的に家族手当と違いはなく、会社によって名称が異なるだけです。
法律上義務付けられているものではなく、会社独自の福利厚生の一環で制定しているので、名称はさまざまです。
3.配偶者手当とは
配偶者手当とは、配偶者のいる労働者に対して会社が支給する手当のことをいいます。
一般的には、配偶者のみに限定した手当はなく、「家族手当」や「扶養手当」という名称で、配偶者や子供それぞれに手当を支給する企業が多いようです。
あまり聞いたことがないという人も少なくはないでしょう。
なお、配偶者手当は法律上で義務付けられていないため、支給制度を設けていない会社もあります。
また、あくまで会社独自の福利厚生の一つであり、名称や支給条件、支給額はそれぞれの企業によって異なります。
家族手当、扶養手当等の支給条件
家族手当や扶養手当等の支給条件は会社によって異なります。
1.扶養者の収入による制限
家族手当の支給対象となる配偶者や子どもの収入に制限をかけている場合が多くあり、その制限は103万円であることが多いようです。
103万円は税制上で所得税がかからず配偶者控除を受けることができる金額の上限であり、国が決めているこの金額を一つの指標としている場合が多いです。
2.同居しているかどうか
支給条件に同居であることを課している場合もあります。
たとえば、両親であっても同居していて収入が制限範囲内であれば支給されます。
3.生計を一にしている
支給条件に同一生計で被扶養者となっていることを条件としている会社も多くあります。
たとえば、学生寮などに入っている子どもや別居している両親であっても仕送り等で同一収入内で生活しているのであれば支給されます。
4.年齢制限
家族手当や扶養手当に、年齢制限を課している場合もあります。
たとえば、子どもは満22歳以下、両親は満60歳以上などとしている企業が多くあります。

家族手当・扶養手当の支給金額の相場
家族手当や扶養手当の金額もまた、各企業によって大きく異なります。
1.公務員の場合
国家公務員の家族手当は一般職の職員の給与に関する法律の概況で明らかになっており、その支給額は家族の年齢などにより細かく規定されています。
- 配偶者(届出をしていなくても、事実上婚姻関係にある者を含む)
- 満22歳になった後の3月31日をまだ迎えていない子、孫
- 満60歳以上の父母、祖父母
- 満22歳になった後の3月31日をまだ迎えていない弟妹
- 重度心身障害者
上記のように分類されており、配偶者は6,500円、子は10,000円、父母等は6,500円となっています。
なお、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる場合は、上記の規定に関係なく、その人数×月額5,000円が加算されます。
このほかの国家公務員の家族手当の細かい規定は、人事院規則により制定されています。
なお、地方公務員は各自治体によって異なりますが、基本的に国家公務員に準じた金額に設定されています。
(参考)人事院勧告(国家公務員の給与)国家公務員の諸手当の概要
2.民間企業の場合
民間企業の大体の相場は配偶者が10,000円、子ども1人につき3,000円から4,000円が相場です。
会社によってかなり大きな差があり、子ども1人につき1,000円しか貰うことができないという会社もありますし、一方で子ども1人に対し20,000円も支給してくれる会社もあります。
3.家族手当、扶養手当の支給割合
家族手当、扶養手当は貰えるのが当たり前であるということではなく、実はかなりの割合でそのような手当が全くない企業があります。
厚生労働省の調査結果(※)によれば、家族手当制度がある事業所は76.5%となっており、およそ4社に1社は家族手当や扶養手当をもらうことができないのです。
(※)「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会報告書」(厚生労働省)
家族手当の今後の流れ
企業の人事管理においてはいかに仕事と家庭の調和を取っていくのかという視点が欠かせないものとなっています。
とりわけ従業員の育児支援に関する企業の取り組みには様々なものがありますが、その中でも多くの企業で行われている施策が家族手当の支給に関するものです。
家族手当に関する近年の見直しの動きは以下のようになっています。
1.改革が進む家族手当
家族手当は、役職手当や通勤手当と並んで、もっとも採用率が高い手当の一つですが、近年、この手当の見直しが多くの企業で進められています。
具体的には、配偶者に対する手当は全体として縮小、もしくは廃止の方向が強まっています。
男性がその世帯の生計を維持し、女性は専業主婦であるとするシングルインカムの考え方の崩壊がその背景にありますが、この流れはもはや決定的であるといえます。
これに対し、子どもに対する手当の考え方は大きくその考え方が二分されます。
一つは配偶者同様、子どもに対する手当も必要ないという考え方、もう一つはむしろ最低限の生活の扶助として、子どもに対する手当を拡充しようとする考え方です。
従業員の各年代における生計費負担を考えた場合、子どもの教育費が大きな割合を占めていることは明らかです。
よって、実際の企業の選択としては後者の子どもへの手当の拡充という動きが大きなトレンドとなっています。
2.子どもへの支援を強める際の選択肢
こうした家族手当の子ども重視の方針を制度化する際には大きく分けて以下の3つの選択肢があります。
(1)子どもへの家族手当支給額の増額
単純に従来の支給額を増やすというシンプルな対応です。
イメージとしては月額5,000円であった手当を10,000円に増額するといったものになります。
(2)子女教育手当の創設
子どもの教育費負担に対する支援ということで、具体的には、高校生および大学生の子どもを持つ従業員については、たとえば月額20,000円といった比較的高額の手当を支給するといった内容となります。
月額20,000円と聞くと非常に高額でコスト負担が大きいと感じられますが、期間限定の手当であるため、実際の負担はそれほどまで大きくなく、また配偶者手当の見直しと併せて考えることで、十分にそのコストを捻出することも可能でしょう。
たとえば、月額20,000円の手当を高校・大学の7年間限定で支給した場合、その総額は子ども1人につき168万円となります。
これに対し、月額15,000円の配偶者手当を支給している場合、従業員が27歳で結婚したとすると、33年間の支給総額は実に594万円にもなります。
これを踏まえれば、配偶者手当を仮に半額に引き下げれば、我が国の平均出生率程度の子女教育手当の原資を確保することは十分に可能となります。
(3)次世代育成支援金(一時金制度)の創設
月額の支給額を増やすのではなく、支給方法自体を見直し、毎月の支給からイベント毎に一時金を支給する方法に変更するしくみです。
たとえば、子どもの出生時、小学校・中学校・高校・大学への各進学時にそれぞれ30万円の祝金を支給するといったイメージです。
この金額だけを見ると高いようですが、その総額は150万円であり、先ほどの子女教育手当よりも少ない原資でこれを導入することができます。
福利厚生が充実しているかどうかは会社選びに重要
家族手当も含めて、福利厚生が充実しているかどうかは仕事選ぶ上で重要な基準です。
家族手当以外にも住宅手当や通勤手当など、会社によって大きく違いますし、すぐに目には見えないものでも退職金制度も重要な一つです。
【就活生の4人に1人が登録!】オファー型就活サイト『OfferBox<オファーボックス>』
OfferBoxは、逆求人サービスにおける利用企業数業界1位です。
しかも、自己分析テストや就活イベントもある逆求人に留まらない就職サイトです。
利用企業数 5600社以上(2019年12月時点の実績)で大手企業・ベンチャー企業・官公庁(経産省)などが利用しています。
オススメするOfferBoxのポイント3つ
- 大手からベンチャーまで数多くの企業からのオファーが来る!
- 高精度な自己分析ができる!
- 単なる逆求人サイトに留まらずイベントが豊富!
学生に対して一斉スカウトメールを送れない仕組みをとっているため、迷惑メールがなく、プロフィールや強みをしっかり見たうえで、スカウトメールが届くので安心です。
また、OfferBoxには高機能な自己分析ができる「AnalyzeU+」と他己分析もできる「適性診断360度」があります。
これらの適性診断の結果をもとに、自己PRをさらに磨くことができます。
さらに、選考直結するインターンや業界研究まで様々なイベントに参加することができます。
まずは、あなたの価値を知るために自己分析からはじめましょう。
無料登録 ☞ OfferBox ![]()
この他にも特色のある就活サイトがあります。
興味のある方はこちらをご覧ください。





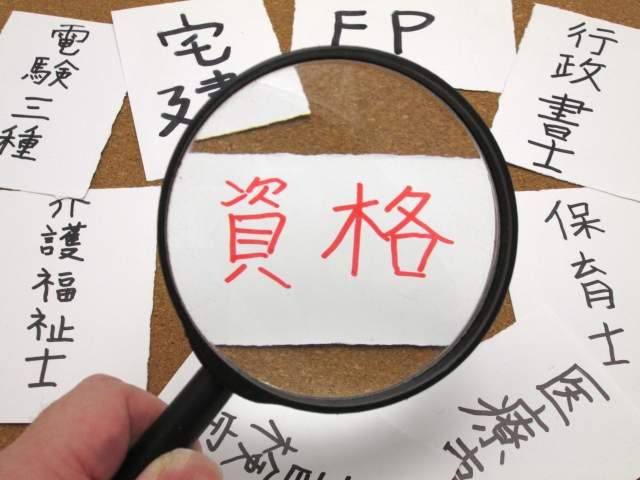

コメント